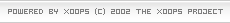これらのキーワードがハイライトされています:カテゴリー/講演 講演
Return to カテゴリー/講演
Total: 45 pages
- CALLで授業をどう変えるか (3825d) [ 「CALLで授業をどう変えるか」 ]カテゴリー/講演 「CALLで授業をどう変えるか」 講師:尾関 修治(名古屋大学) 講師紹介:小栗成子(中部大学) CALLつまりLLも含めたICTを利用した語学教育で何が行なわれているか概観し、CALLによって授業がどう変わっていくのか、魅力的な授業をどう組み立てるのか等、コミュニケーション教育とICTとの関係について具体的な手法の解説をしつつ提案する。 [ 戻る ]
- CALL研究を考える (3097d) [ CALL研究を考える:ひと・もの・ことの視点から ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ CALL研究を考える:ひと・もの・ことの視点から 会場・時間 講演概要 資料 CALL研究を考える:ひと・もの・ことの視点から 講師:住 政二郎(流通科学大学) 会場・時間 カンファレンスホール 16:45-17:45 講演概要 本発表は3つのパートからなる。最初に,CALL研究を「ひと・もの・こと」の3点から捉え直すエコロジカル・パースペクティブについて紹介する。次に,その具体例として,発表者が現在取り組んでいる,多段階反応モデルを活用した学習支援システムの開...
- CAN-DOリストを活用した小中高大の英語教育 (3832d) [ CAN-DOリストを活用した小中高大の英語教育 ]カテゴリー/講演 CAN-DOリストを活用した小中高大の英語教育 講師:高橋 美由紀(愛知教育大学) 会場・時間 3011講義室 10:45-12:00 講演概要 筆者等は、「CEFR」が採用した「CAN-DO」リスト形式に則り、日本人学習者のために、英語到達度指標「CEFR-J」を作成しました。「CEFR-J」の学習到達度指標は、language biographyの中で自分の学習目標や学習プロセスのモニター、結果の評価などに用いることができます。また、教材のレベル設定等に基づき、指導のためにも使...
- Crisis or Opportunity (1082d) [ Crisis or Opportunity:コロナ禍が与えてくれた大学教育再考のための試練 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ Crisis or Opportunity:コロナ禍が与えてくれた大学教育再考のための試練 会場・時間 要旨 配布資料 Crisis or Opportunity:コロナ禍が与えてくれた大学教育再考のための試練 近藤 祐一(立命館アジア太平洋大学) 会場・時間 Zoom Room 1 10:15-11:45 要旨 このコロナ禍は全学生の半数が留学生で、国内生の1/4を毎年海外に派遣している立命館アジア太平洋大学(APU)には大きな試練であった。しかし、これまでの...
- ICTを活かした英語教育―”使われる”から”使う”へ― (3108d) [ ICTを活かした英語教育 ―"使われる"から"使う"へ― ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ ICTを活かした英語教育 ―"使われる"から"使う"へ― 概要 講師略歴 尾関による当日メモ ICTと英語教育 開発教...できるリソースやツールの種類は飛躍的に増えつつあります。選択肢が多いことは、喜ばしいことであると当時に、利用する我々教師の選択眼がますます問われることになることを意味しています。本講演では、ICTに“使われる”から “使う”へシフトするために我々英語教師が何に留意すべきかについて、私のこれまでのICT...
- MenuBar (2247d) [ 最近の支部研究大会一覧 ]最近の支部研究大会一覧 第91回支部研究大会(2018年度春季) 第90回支部研究大会(2017年度秋季) 第89回支部研究大会(2017年度春季) 第88回支部研究大会(2016年度秋季) カテゴリー カテゴリー一覧 支部大会 講演 研究発表 シンポジウム ワークショップ 研究部会 個人 事務局 用語・インデックス 最新の10件 2024-04-15 外国語教育基礎研究部会 2024-03-26 2023年度報告論集 名古屋大学大学院人文学研究科英語教育学分野連続公開講座(4)(キソケン共催) 2...
- Promoting English Use Through Digital Badges (3133d) [ Promoting English Use Through Digital Badges ]カテゴリー/講演 Promoting English Use Through Digital Badges 講師:Gordon Bateson(高知工科大学) 会場・時間 2号館B棟501講義室 10:20-11:40 概要 This presentation will examine the use of the digital badges to support and encourage the use of English by students inside and outside the...
- SDGs時代のグローバル教育 (1816d) [ SDGs時代のグローバル教育:グローバルシティズンシップを育む ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ SDGs時代のグローバル教育:グローバルシティズンシップを育む 会場・時間 要旨 配布資料 SDGs時代のグローバル教育:グローバルシティズンシップを育む 石森 広美(宮城県仙台二華高等学校) 会場・時間 1階メアリーホール 10:15-11:40 要旨 グローバル社会で必要なのは、単なる知識ではなく、その活用能力であり、言語や文化、風習や価値観等が異なる多様な人々と創造的かつ建設的に意見を交換し合い、理解し合い、協調し、共に課題解決のために手を取り合うことので...
- “Distance English” in the Post-COVID-19 Era (1267d) [ “Distance English” in the Post-COVID-19 Era: Educational Opportunities and Challenges ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ “Distance English” in the Post-COVID-19 Era: Educational Opportunities and Challenges 時間 要旨 配布資料 “Distance English” in the Post-COVID-19 Era: Educational Opportunities and Challenges Christopher Mayo(皇學館大学) 時間 10:45-12:10 要旨 This pre...
- “語彙の学び”を科学する:小中高大の連携の視点 (3329d) [ 講演「“語彙の学び”を科学する:小中高大の連携の視点」 ]カテゴリー/講演 講演「“語彙の学び”を科学する:小中高大の連携の視点」 石川 慎一郎(神戸大学) 発表概要 第2言語の習得において語彙が決定的に重要であることは広く指摘される通りですが、実際の教育現場では,語彙学習はしばしばカリキュラムの外に追いやられ,学...単ですが,少し立ち止まって考えてみると、「いったい何を覚えさせればいいのか」「どのように覚えさせればいいのか」「そもそも語彙を覚えるとはどういうことなのか」といった基本的な問いにすら、なかなか明白な答えを出せないことに気が付きます。 本...
- オープンサイエンス時代の外国語教育研究 (1594d) [ オープンサイエンス時代の外国語教育研究 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ オープンサイエンス時代の外国語教育研究 会場・時間 要旨 配布資料 オープンサイエンス時代の外国語教育研究 石井 雄隆(千葉大学) 会場・時間 情13教室 10:15-11:40 要旨 本講演では,オープンサイエンスを巡る社会的動向を踏まえながら,外国語教育研究の今後の在り方について検討したいと思います。オープンサイエンス(...の観点から考えられます。それぞれ,(1)研究成果や研究資料の公開・共有,(2)新たな学術の次元の追求,(3)社会との協働の3点です。本...
- タスクと学習ストラテジー:高等学校新学習指導要領の実施にむけて (3329d) [ タスクと学習ストラテジー:高等学校新学習指導要領の実施にむけて ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ タスクと学習ストラテジー:高等学校新学習指導要領の実施にむけて 概要 当日記録 学習ストラテジーの定義と実際 自律した学習者とは何か 諸外国の例 具体的な指導...確認された。学習ストラテジー指導というと単に学習を助ける技術指導という印象があるが,学習ストラテジー指導の真の目的は自律した学習者を育て,学習者の「生きる力」を育むことにある。この講演では,そのような学習ストラテジーの理論的背景と概要,タスクを利用した学習ストラテジー指導の実践例を紹介する。 講師:尾...
- タスクに基づく言語教授法とはなにか (2892d) [ タスクに基づく言語教授法とはなにか編集--その考え方と最新の動向 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ タスクに基づく言語教授法とはなにか編集--その考え方と最新の動向 会場・時間 発表概要 配布資料 タスクに基づく言語教授法とはなにか編集--その考え方と最新の...り、近年ではさまざまな周辺分野の知見を取り入れながら発展してきています。本発表では、TBLTの基本的な考え方、提唱された背景および関連研究、近年の動向、そして残されている問題点を、講演者が行ってきた研究に触れながらお話したいと思います。本発表の中で扱う内容は以下のとおりです。まず、(a)最初期にTBL...
- ニュースのジェンダー・バイアス (707d) [ ニュースのジェンダー・バイアス:東京オリンピック 2020 から考える ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ ニュースのジェンダー・バイアス:東京オリンピック 2020 から考える 会場・時間 要旨 配布資料 ニュースのジェンダー・バイアス:東京オリンピック 2020 から考える 小林 直美(愛知工科大学) 会場・時間 Zoom Room 1 10:15-12:00 要旨 東京オリンピックでは女子選手の参加率は史上最多の49%に達した。スポーツでは参加率や競技種目においてジェンダー平等が進んでいるように思われるが、ニュースにおけるジェンダー・バイアスは根強く存在する。学...
- 人工知能型機械翻訳にできること、できないこと (1989d) [ 人工知能型機械翻訳にできること、できないこと ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 人工知能型機械翻訳にできること、できないこと 会場・時間 要旨 配布資料 人工知能型機械翻訳にできること、できないこと 将棋や碁などで人間に勝つようになった人...という新しい人工知能型の自動翻訳システムでのサービスを開始した。これらのシステムは、流暢さは完ぺきに近く、正確さも非常に高くなっていて、人間と同じ程度の翻訳が可能となっている。この講演では、ゲームに勝つことに比べて、言葉を理解することがコンピュータにとって難しい理由に触れて、人工知能型翻訳システムの現...
- 分厚い中間層の学生を対象としたグローバル人材育成方策と成果 (3084d) [ 分厚い中間層の学生を対象としたグローバル人材育成方策と成果 ]カテゴリー/講演 分厚い中間層の学生を対象としたグローバル人材育成方策と成果 講師:小野 博(福岡大学) 会場・時間 311大講義室 10:45-12:00 講演概要 福岡大学では、分厚い中間層の学生(TOEIC350〜450)をグローバル人材に育成する英語教育プログラムを平成25年度から本格的に始めることとし、それに先駆けて、...は、 (4)欧米で盛んなコミュニケーション能力育成方法である英語によるドラマメソッド (5)ロス在住ジャーナリストによる「やさしい英語による授業」や大学関係者・経済人の...
- 反転授業から学ぶICT利用による産出・創造活動の支援 (3311d) [ 反転授業から学ぶICT利用による産出・創造活動の支援ーmラーニング、無償ツール、クラウドの活用 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 反転授業から学ぶICT利用による産出・創造活動の支援ーmラーニング、無償ツール、クラウドの活用 会場・時間 概要 資料等 反転授業から学ぶICT利用による産出・創造活動の支援ーmラーニング、無償ツール、クラウドの活用 講師:神田 明延(首都大学東京) 会場・時間 概要 グローバル化、情報化が強調される時代になり、これまでの理解と記憶を主にする学習観ではなく、協調・創造等を含めた学習活動が求められるようになってきた。言語教育におけるこうした高次の学習活動を活性化す...
- 否定フィードバックの言い直し(recasts)について考える (2982d) [ 否定フィードバックの言い直し(recasts)について考える ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 否定フィードバックの言い直し(recasts)について考える 会場・時間 講演概要 資料等 否定フィードバックの言い直し(recasts)について考える 講師:酒井 英樹(信州大学) 会場・時間 16:00-17:10 502室 講演概要 言い直し (recasts) は、第二言語習得研究において最も多くの焦点があてられてきた否定フィードバックの1つです。また、教育的にも、Focus on Form を促進する1つの手段として注目されてきました。なぜ、第二言語習...
- 外国語学習の動機づけを探る (2701d) [ 外国語学習の動機づけを探る:動機づけ要因、動機づけ方略、情意要因との関係を通して ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 外国語学習の動機づけを探る:動機づけ要因、動機づけ方略、情意要因との関係を通して 会場・時間 講演概要 資料等 外国語学習の動機づけを探る:動機づけ要因、動機づけ方略、情意要因との関係を通して 講師:竹内 理(関西大学 外国語学部・大学院外国語教育学研究科) 会場・時間 16:00-17:50 DWレセプションホール 講演概要 本講演では、冒頭で、講演者のこれまでの研究活動の流れを振り返り、なぜ今回、このテーマを選んだかを説明する。その後、動機づけ研究の外国語(...
- 外国語教室での口頭訂正フィードバック (867d) [ 外国語教室での口頭訂正フィードバック:研究成果と教育現場への応用 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 外国語教室での口頭訂正フィードバック:研究成果と教育現場への応用 会場・時間 要旨 配布資料 外...ある。そもそも誤りの訂正には効果があるのだろうか。あるのであれば、どのような誤りを、どう訂正したらいいのだろうか。 本講演では、第二言語習得の観点から、口頭訂正フィードバックの役割・効果について考える。...する理論と実践の橋渡しができるような話にしたいと考えている。 配布資料 LET講演「口頭訂正フィードバック」(大関).pdf 第97回支部研究大会 [ 戻る ]
- 外国語教育研究を実りあるものにするために (3739d) [ 外国語教育研究を実りあるものにするために:測定すること・整理すること・分析すること・解釈すること ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 外国語教育研究を実りあるものにするために:測定すること・整理すること・分析すること・解釈すること 時間 会場 講演概要 外国語教育研究を実りあるものにするために:測定すること・整理すること・分析すること・解釈すること 講師:前田 啓朗(広島大学) 時間 16:30-17:30 会場 ファカルティラウンジ 講演概要 外国語教育に携わる私たちにとって,測定すること(成績評価やデータ収集など)・整理すること(データの電子化など)・分析すること(作図や統計処理など)・解...
- 大学の英語教育の現実とその将来に向けて (3329d) [ 大学の英語教育の現実とその将来に向けて ](以下は尾関が当日とっていたメモ) カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 大学の英語教育の現実とその将来に向けて 大学の英語教育の枠組み(大綱化) 大学英語教育の現状(現代GP) もう一つの現状:問題点 将来 私の授業 大学の英語教育シリーズ 大学の英語教育の現実とその将来に向けて 大学の英語教育の枠組み(大綱化) 1991年大学設置基準の改正:一般教育内の区分の廃止等->教養部の改組解体が進行 本来は教養教育の充実・教育課程の体系化を狙ったもののはずだった その後も教養教育の重視について答申...
- 大学英語教育とESP (3329d) [ 講演「大学英語教育とESP」 ](以下は尾関が当日とったメモ) カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 講演「大学英語教育とESP」 尾関のメモ 大学英語教育の流れ(おさらい) EGST教育(名工大) e-learningによる英語教育 工学英語研究;教員側の評価 今後の課題 会場からの質問 講演「大学英語教育とESP」 講師:石川 有香(名古屋工業大学) 演題:「大学英語教育とESP」 ハンドアウトあり 尾関のメモ 大学英語教育の流れ(おさらい) 教養から道具化へ 数値評価へ EGST教育(名工大) EGPとESP; EAP/EE...
- 小中高大におけるアクティブ・ラーニングの展開--早稲田大学の事例から (2720d) [ 小中高大におけるアクティブ・ラーニングの展開--早稲田大学の事例から ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 小中高大におけるアクティブ・ラーニングの展開--早稲田大学の事例から 会場・時間 発表概要 配布資料 小中高大におけるアクティブ・ラーニングの展開--早稲田大...ープワーク、ディベートなどのさまざまなアクティブ・ラーニング手法を紹介しており、またそれらをアイスブレーク、導入、展開、リフレクション、評価などの授業フェーズごとに紹介している。本講演では、早稲田大学におけるアクティブ・ラーニングの展開として、『対話型、問題発見・解決型教育の手引き』の内容に触れながら...
- 情報メディアへの向き合い方:教育の果たす役割 (3329d) [ 情報メディアへの向き合い方:教育の果たす役割 ]カテゴリー/講演 情報メディアへの向き合い方:教育の果たす役割 講師:水野 義之(京都女子大学) 大学での情報メディア系の基礎教育は、社会状況の国 際化や情報化等への対応が特に必要とされる科目の一つである。ここではこの問題を次の3つの観点から議論する。第一にキャリア教育や社会人基礎力・学士力など健全な市民社会を育てる視点、第二に全国アンケート分析の視点、第三に大学・情報系関連学会等によるカリキュラム改革の視点である。事例として京都女子大学で行った10年ほどの情報教育改革の経緯を紹介しつつ、また英語の...
- 教育実践の成果を確認するためのデータ処理 (3330d) [ 教育実践の成果を確認するためのデータ処理 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 教育実践の成果を確認するためのデータ処理 会場・時間 講演概要 配布資料 教育実践の成果を確認するためのデータ処理 講師:前田 啓朗(広島大学 外国語教育研究センター) 会場・時間 2階ホール 10:45-12:00 講演概要 日々の指導と評価に関わるものや,研究のために改めて収集したものなど,教育・研究に携わる私たちの周りには多種多様なデータがあります。また,今後の改善に繋げることを目的とし指導を振り返ったり,教育実践の成果を確認したりして,報告することが求...
- 新人奨励賞受賞記念講演会 (3352d) [ 新人奨励賞受賞記念講演会 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 新人奨励賞受賞記念講演会 要項 プログラム 昼食 参考 新人奨励賞受賞記念講演会 2014年度外国語教育メディア学会学会賞新人奨励賞を受賞した草薙邦広氏(名古屋大学大学院生・学振研究員)と氏の指導教員で共同研究者でもある山下淳子先生(名古屋大学大学院国際開発研究科)の記念講演会を開催します。 要項 期日:2015年2月21日(土) 10:00-12:00 会場:名古屋大学東山キャンパス 文系総合館7F カンファレンスホール 〒464-8601 愛知県名古屋市千種...
- 明示的および暗示的知識とはなにか,どうやって測るか,なにに役立つか (3062d) [ 明示的および暗示的知識とはなにか,どうやって測るか,なにに役立つか ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 明示的および暗示的知識とはなにか,どうやって測るか,なにに役立つか 会場・時間 講演概要 資料等 明示的および暗示的知識とはなにか,どうやって測るか,なにに役立つか 講師:草薙 邦広(名古屋大学大学院生・日本学術振興会特別研究員) 会場・時間 文系総合館7F カンファレンスホール 10:00-10:50 講演概要 本講演では,第二言語/外国語の明示的および暗示的知識に関わるさまざまなことがらに焦点をあてて,その理論的枠組み,測定法,そして教育実践へのかかわりにつ...
- 第76回大会講演 (3620d) [ 「“語彙の学び”を科学する:小中高大の連携の視点」 ]カテゴリー/講演 「“語彙の学び”を科学する:小中高大の連携の視点」 講師:石川 慎一郎(神戸大学) 報告:尾関 修治 参加者数:72名 概要:近年の語彙研究のトレンドとしてコーパスの利用を紹介し...の語彙指導について、語彙の選定と指導の具体的な内容について実証的に研究していることを解説した。 会場の様子:英語教員を志望する学生も参加し、講師が参加者一人一人に語りかける熱意ある講演であった。 第76回支部研究大会
- 第77回大会講演 (3620d) [ 「英語の強弱アクセントの知覚:その語彙力と聴解能力への影響」 ]カテゴリー/講演 「英語の強弱アクセントの知覚:その語彙力と聴解能力への影響」 講師:玉岡 賀津雄(名古屋大学) 報告:石川 有香 参...の音声学習モデルを設定し、アクセントを含めた音韻練習を徹底して行い、音声知覚の自動化を促す重要性を説く。 会場の様子:講演後の質疑応答では、今後の研究の方向性や研究手法の発展的応用の可能性について活発な....lang.nagoya-u.ac.jp) 第77回支部研究大会 第76回大会講演 第75回大会講演 第74回大会講演 第73回大会講演 第72回大会講演 ...
- 第78回大会講演 (3620d) [ 「テストデータを分析する:古典的テスト理論・項目反応理論・潜在ランク理論による学力評価」 ]カテゴリー/講演 「テストデータを分析する:古典的テスト理論・項目反応理論・潜在ランク理論による学力評価」 講師:荘島 宏二郎(大学入試センター研究開発部) 報告:杉野 直樹(立命館大学) 参加者数:約30名 概要:古典的テスト理論・項目反応理論・潜在ランク理論の3つのテスト理論について、予定された2時間のほぼ全てを使って説明された。講演では、氏が開発されたexametrikaを使って実際にデータ分析を行い、出力の違いを確認することで、それぞれのテスト理論に基づく分析が、テストとその受検者の学力評価...
- 第79回大会講演 (3620d) [ 認知言語学を参照した英語学習支援法--言語の部分的動機づけと日英語の認知様式の違いに目を向けさせる授業実践-- ]カテゴリー/講演 認知言語学を参照した英語学習支援法--言語の部分的動機づけと日英語の認知様式の違いに目を向けさせる授業実践-- 今井 隆夫 愛知みずほ大学 会場参加者数:40名 講師紹介・報告:... 概要 氏が提唱する「感覚英文法」は形式と形式の対訳ではなく、形と意味(イメージ)の結びつきを学習するための道具立てとして、誰もが理解できる認知言語学の考え方を利用するものである。講演では、認知言語学の理論的な背景説明に加え、「なぜAは言えるのにBは言えないのか」というクイズ形式の実例について参加者ど...
- 第80回大会講演 (3620d) [ 教育実践の成果を確認するためのデータ処理 ]カテゴリー/講演 教育実践の成果を確認するためのデータ処理 前田 啓朗(広島大学 外国語教育研究センター) 会場参加者数:30名 講師紹介・報告:柳 善和(名古屋学院大学) 概要 「教育実践の成果を確認するためのデータ処理」というタイトルで、これまで一般的に使われている統計分析に触れながら、「教育実践の成果」という観点から、注意すべき点を指摘していただいた。具体的にはヒストグラム、散布図などの重要性、相関係数使用の際の留意点、階層的クラスタ分析の使用法などである。これらのことから、「統計的に有意であ...
- 第81回大会講演 (3620d) [ 第81回大会講演 ]カテゴリー/講演 第81回大会講演 分厚い中間層の学生を対象としたグローバル人材育成方策と成果 講師:小野 博(福岡大学・昭和大学客員教授、日本リメディアル教育学会ファウンダー) 会場参加者数:約35名 司会・報告:鈴木 薫 名古屋学芸大学短期大学部 概要 英語集中学習だけでなく、コミュニケーション能力を高めるための役者による指導や、留学生との共同作業によって徹底的に準備をした後に、2週間の海外研修を実施することで、TOEICスコアを平均110点以上向上させた画期的な取り組みが報告された。e-lea...
- 第82回大会講演 (3620d) [ 第82回大会講演 ]カテゴリー/講演 第82回大会講演 CAN-DOリストを活用した小中高大の英語教育 講師:高橋 美由紀(愛知教育大学) 会場参加者数:約16名 司会・報告:犬塚 章夫 (刈谷市立小垣江小学校) 概要 まずヨーロッパで行われているCEFRがどのような目的で作られているのか、どのようなフレームワークと記述であるのかを述べ、それと比較しながら、日本の英語教育環境に当てはめたCEFR-Jの特徴について説明があった。CEFR-Jは、CEFR同様、聞く・読む・話す(やりとり・発表)・書くの5つの観点でCAN-D...
- 第83回大会講演 (3105d) [ 第83回大会講演 ]カテゴリー/講演 第83回大会講演 非グローバル化時代の英語教育--戦後史と社会統計から考える 司会・報告:福田 純也 (名古屋大学大学院生) 会場参加者数:30名 概要 講演では,グローバル化と英語教育振興を結びつけた教育観を「相対化」することを試み,歴史的観点から英語教育振興とグローバル化の関連を検討した。「当たり前」と考えられている言説に疑問を投げかけ,英語教育目的を考える際に重要な視点を提供した。質疑では,なぜ日本は他言語ではなく「英語教育」の振興に傾いたのかという点などに関して議論が交わさ...
- 第86回大会講演 (3081d) [ 第86回大会講演 ]カテゴリー/支部大会カテゴリー/講演 第86回大会講演 Promoting English Use Through Digital Badges 司会・報告:大滝 宏一(金沢学院大学) 会場参加者数:30名 概要 大学の英語教育において、学生の積極的な英語の使用を促すための取り組みとして、LMSを使った様々な授業や活動が講師によって紹介された。特に、Digital Badgeと呼ばれる、オンライン上の褒賞システムの可能性について、その仕組みや具体的な運用方法を交えながら、紹介された。 第86回支部研...
- 第二言語のリスニング能力と音韻的作動記憶との関連性 (2550d) [ 第二言語のリスニング能力と音韻的作動記憶との関連性--課題・実験デザインの立案から、データ収集・分析、論文執筆に至るまで-- ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 第二言語のリスニング能力と音韻的作動記憶との関連性--課題・実験デザインの立案から、データ収集・分析、論文執筆に至るまで-- 会場・時間 発表概要 配布資料 ...ング能力と音韻的作動記憶の関連性については必ずしも一致した見解が報告されているわけではなく,その理由の一つに作動記憶を測定するテストの種類や項目に一貫性がないことが挙げられます。本講演では,2016年度外国語教育メディア学会の論文賞を受賞した研究について,その背景から,課題・実験デザインの立案,実験項...
- 第二言語読解のコンポーネント (3062d) [ 第二言語読解のコンポーネント:メタ分析と日本の中等教育レベルの横断的研究から ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 第二言語読解のコンポーネント:メタ分析と日本の中等教育レベルの横断的研究から 時間 会場 講演概要 第二言語読解のコンポーネント:メタ分析と日本の中等教育レベルの横断的研究から 講師:山下 淳子(名古屋大学) 時間 11:00-11:50 会場 文系総合館7F カンファレンスホール 講演概要 文章を読んで理解するという行為は、熟達した読み手にとっては無意識なまでに順調に遂行されますが、発達途上の読み手にとっては様々な原因でそのプロセスが滞り理解が阻害されます。読...
- 脳機能にもとづいた言語の発達と学習のメカニズム (3448d) [ 脳機能にもとづいた言語の発達と学習のメカニズム ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 脳機能にもとづいた言語の発達と学習のメカニズム 会場・時間 講演概要 資料等 脳機能にもとづいた言語の発達と学習のメカニズム 講師:萩原 裕子(首都大学東京) 会場・時間 15:15-16:45 講演概要 言語を獲得していく時期やそのプロセスは、母語では言語の違いに関わらず共通していますが、第二言語や外国語の場合は、学習開始年齢、習熟度、接触量、学習環境、教授法など、さまざまな要因が絡んでいて複雑です。本講演では、最近の脳科学の知見をもとに脳の発達の仕組みを概観...
- 言語の可視化をめぐって (2271d) [ 言語の可視化をめぐって:こころと言葉の交響 ]カテゴリー/講演 言語の可視化をめぐって:こころと言葉の交響 講師:石川 慎一郎(神戸大学) 会場・時間 16:00-17:30 キャッスルホール1階1102教室 講演概要 先日,あるサイト上で自分自身が「第2言語習得論の研究者」と紹介されていることを知った。自分ではそのように考えたことはただの一度もなかったので,ずいぶん驚いたのだが,一般に,研究者には何らかのラベルが張られることが多い。「**の研究者」「**の紹介者」「**の大家」といったものである。では,私なら自分自身にどんなラベルを張るか考え...
- 認知言語学を参照した英語学習支援法 (3331d) [ 認知言語学を参照した英語学習支援法 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 認知言語学を参照した英語学習支援法 講師 概要 ハンドアウト 認知言語学を参照した英語学習支援法 ―言語の部分的動機づけと日英語の認知様式の違いに目を向けさせる授業実践― 講師 今井 隆夫 愛知みずほ大学 概要 本講演では、「感覚英文法」に基づく授業実践の例について理論も交えながらお話しします。「感覚英文法」とは、普通の感覚を持つ人なら...f. I‘d rather eat table. (Langacker)という発話はどのようなTPOなら可能か? 今回の...
- 語彙学習の自律と継続を支援するICT活用 (2194d) [ 語彙学習の自律と継続を支援するICT活用:ウェブとアプリの連携 ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 語彙学習の自律と継続を支援するICT活用:ウェブとアプリの連携 会場・時間 要旨 その他 配布資...用:ウェブとアプリの連携 田中 洋也(北海学園大学) 会場・時間 2階 2217教室 10:15-11:40 要旨 本講演は、講師がこれまで開発に携わったウェブ・アプリケーションLexinote、スマー...テムは、個人の学習記録を共有することで統合的な語彙学習支援を可能にしている。 講演では、両システムと同じく講師が制作した定型表現学習アニメーション教材を用い...
- 量的データの分析・報告で気をつけたいこと (2846d) [ 量的データの分析・報告で気をつけたいこと ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 量的データの分析・報告で気をつけたいこと 時間 会場 講演概要 配布資料 量的データの分析・報告で気をつけたいこと 講師:水本 篤(関西大学) 時間 11:00-12:00 会場 ファカルティラウンジ 講演概要 外国語教育研究では,現在,量的データを用いた論文や発表が大半を占めていますが,その分析や報告では,再現性に乏しい不十分な方法が用いられていることがあります。今回の講演では,特に『英語教師のための教育データ分析入門』(前田・山森,2004)や『外国語教育...
- 非グローバル化時代の英語教育--戦後史と社会統計から考える (3624d) [ 非グローバル化時代の英語教育--戦後史と社会統計から考える ]カテゴリー/講演 ページ内コンテンツ 非グローバル化時代の英語教育--戦後史と社会統計から考える 会場・時間 講演概要 資料等 非グローバル化時代の英語教育--戦後史と社会統計から考える 講師:寺沢 拓敬(日本学術振興会特別研究員(PD)) 会場・時間 301講義室 14:00-15:15 講演概要 本講演では、戦後史と社会統計の2つの観点から、私たちが馴染んできた「当たり前」の英語教育観の相対化を試みたいと思います。 グローバル化が進んでいる"とされる"現代、英語教育の重要性は...
Total: 45 pages
Counter: 5470,
today: 1,
yesterday: 1